子どもにパソコンを与えるメリット・デメリット。何年生からがよい?

子どもにパソコンを与えるメリット・デメリットは何?
子どもにパソコンを与えるなら、小学校何年生からがよい?
そんな疑問はありませんか?
最近、インターネットの普及が進んだり、パソコンを活用して授業を行う学校が増えたりしたことで、“家庭でのパソコン活用方法” に悩む保護者が増えています。
いまや、パソコンは生活必需品と言っても過言ではありません。
仕事や学習でパソコン(PC)を使う場面が増えているので、時代に取り残されないよう、早くから子どもに与えておいた方が良い思う意見もあります。
ただ、小さい頃からパソコン(PC)に触れるメリットがある一方で、子どもに早くからパソコン(PC)を与えることで生じるデメリットがあることにも注意が必要です。
この記事では、子どもにパソコンを与えるメリット・デメリットや、何年生から与えるのが良いのかといった目安などについてお伝えします。

目次
子どもにパソコンを与える6つのメリット
最近、小学校低学年など、小さな頃から子どもにパソコン(PC)を与える親が増えているのは、子どもにパソコンを与えるメリットとして、下記のような理由があるからです。
< 子どもにパソコンを与えるメリット一覧 >
メリット1. パソコンの基本的操作が学べる
メリット2. 辞書の代わりになり、知識が増える
メリット3. 遠隔で学習ができる
メリット4. 効率の良い学習ができる
メリット5. 自主性が育てられる
メリット6. クリエイティブな活動に役立つ
メリット1. パソコンの基本的操作が学べる

子どもにパソコンを与えるメリットの1つ目として、”パソコンの基本的操作が学べる” という点は、欠かせないポイントです。
小さい時から、パソコン(PC)に触れる機会を与えることで、”タイピングの仕方” や、”マウスの使い方”、”ファイルのダウンロード・アップロード方法”、”デスクトップ画面の見方” など、日常生活でも使えるパソコンの基本的操作を学ぶことができます。
早くから子どもにパソコンを与えておくことで、小学校・中学校・高校での授業中はもちろん、社会に出た時に必要な基礎知識を自然と身につけることができるので、就職時などに困らなくなる可能性があるんですね。
実際、社会に出た時に、パソコンの基本操作が難なくできるのかどうかは、就職の難易度を大きく左右します。
大人になってから、急いでパソコン教室に通うのではなく、小さな頃からパソコンに慣れておくことで、大人になった時に抵抗感なくPCを操作できるという強みが生まれるのは、大きなメリットだと言えるでしょう。
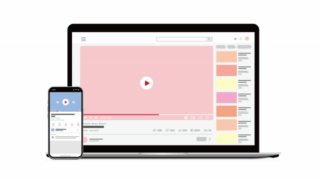
メリット2. 辞書の代わりになり、知識が増える
子どもにパソコンを与えるメリットの2つ目として、辞書の代わりになり、知識が増える可能性があることがあげられます。
パソコンがあれば、”自分の気になったこと” や “疑問に思ったこと” を、インターネットを介してすぐに調べることが可能です。
紙の辞書があれば、漢字や言葉の使い方などを調べることはできるものの、最新の情報を知ることが難しかったり、調べたいことにたどり着くまでに時間がかかったりしますよね。
でも、パソコン(PC)であれば、「たくあんが黄色いのはなんで?」など、”口語” で検索ができるほか、ChatGPTなど、無料で使えるAIに “チャット形式” で追加でどんどん質問し、回答を得ることも可能です。
Web上に検索結果がでてくるほか、YouTubeなどの “動画配信サイト” を使って調べることもできるので、文章だけでなく、動画や画像を観ることで、より分かりやすく理解できます。
パソコンを使って調べる習慣を子どもの頃から身につけることで、自然と知識が深まる可能性があるんですね!
とくに、中学受験など、早期にさまざまな知識を必要とする場合は、小学生の頃からパソコンを与えるメリットが大きいと言えるでしょう。

メリット3. 遠隔で学習ができる
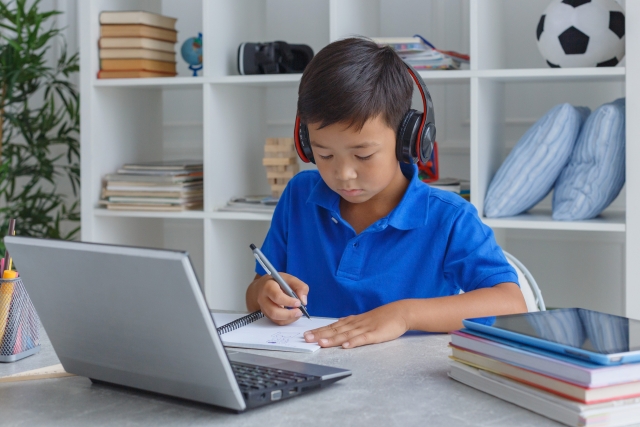
子どもにパソコンを与えるメリットの3つ目は、PCを使って “遠隔(オンライン)での学習が可能になる” という点です。
パソコンを活用することで、オンライン学習が可能となるため、体調不良や何らかの理由で学校を欠席したときの “個別授業” や、”習い事” の一環として遠隔授業にも対応できるようになります。
コロナ禍に入り、出社せずに在宅で仕事をする在宅ワーカーが増えたように、最近は、私立の学校を中心に、”在宅で授業を受ける機会” が増えてきています。
パソコン(PC)を使うことで、日本各地はもちろん、”世界中の講師とつながることができる” ので、バイオリンのレッスンを一流の講師からオンラインで受けたり、フィリピンのセブ島にいる講師からオンライン英会話の授業を月数千円のレッスン料で受講することも可能です。
子どもにオンラインでの学習をさせたい場合は、とくに、PCの導入を検討してみると良いでしょう。

メリット4. 効率の良い学習ができる
子どもにパソコンを与えるメリットの4つ目は、”効率の良い学習ができる” という点です。
パソコンには、さまざまなアプリやWebサイトへのアクセスができるので、”一人ひとりの学習能力に合った勉強法” が見つけやすくなります。
学校で行う一斉授業の場合、”周りの子たちの理解度の速さに付いていけない子” が出てしまったり、逆に、”周囲よりも理解度が速く飽きてしまう子がいたり” するなど、“個々の学習速度や興味関心に合わせた教育ができない” という課題が生じます。
その点、パソコン(PC)を使って学習する場合は、”問題の難易度を調整” したり、”苦手な科目を重点的に学習したり” など、子どもに合わせてカスタマイズした学習が可能になります。
子どもの学習意欲を損なわない形で、”効率の良い学習” ができるという点は、子どもにパソコンを与えるメリットの1つでしょう。
メリット5. 自主性が育てられる

子どもにパソコンを与えるメリットの5つ目は、”自主性が育てられる” という点です。
パソコンがあれば、”気になったこと” や “疑問に思ったこと” をすぐに調べられたり、今後の活動に繋げられたりします。
自然と子どもの好奇心が刺激され、勉強・学びの楽しさを実感できるようになるので、自主的に学習に取り組む習慣がつきます。
実際、大人になってからも、何かわからないことがあったとき、自分で調べることができるのかは重要なポイントですよね。
小さい頃から、PCやインターネットに触れる機会があることで、自主的に解決する能力が高まるほか、たくさんある情報の中で、主体性を持って情報の取捨選択を行う習慣が身につくのは、子どもにパソコンを与えるメリットです。
メリット6. クリエイティブな活動に役立つ

子どもにパソコンを与えるメリット、さいごの6つ目は、”クリエイティブな活動に役立つ” という点です。
インターネットの普及に伴い、子どもたちが憧れる職業、親が将来子どもに就かせたい職業も変わってきました。
最近、男の子を中心に「小学生がなりたい職業ランキング」で上位にランクインする “エンジニア・プログラマー” は、高収入が期待でき、就活時に就職もしやすいことから、親からも人気の職業です。
また、”YouTuber” や “イラストレーター” など、クリエイティブな活動をする職業も根強い人気があり、小学生・中学生・高校生のうちからSNSでの配信を行うことで、大学への入学を有利に進めたり、インフルエンサーとして就活を有利に進めたりする学生も少なくありません。
“エンジニア・プログラマー”、”YouTuber”、”イラストレーター” などの職業に就くためには、プログラミングの知識や、動画編集の知識、Webデザインに関する知識が欠かせず、”早いうちに子どもにパソコンを与えておく” ことで、苦でなく将来役に立つスキルを身につけられるのは、子どもにPCを与える大きなメリットです。
小学生の習い事として、”プログラミング” が人気になっているのも、時代の変化とともに、PCスキルが不可欠になっているからなんですね!
子どもにパソコンを与える3つのデメリット
このように、子どもにパソコンを与えることで得られるメリットはたくさんあります。
基本的には、小さい頃からパソコンに触れる機会を作ることは、有益だと言えるでしょう。
ただ一方で、子どもにパソコンを与えるデメリットもあるので、注意してください。
デメリット1. 視力の低下

子どもにパソコンを与えるデメリットとして、”視力が低下しやすい” 可能性がある点には、注意が必要です。
“長時間パソコンの画面を見続けてしまう” と、目に大きな負担がかかります。
とくに、子どもの目は、大人の目よりも光の影響を受けやすいと言われているので、注意が必要です。
子どもがパソコンを触っている間は、”適度に休憩を挟む”、”子どもが目を近づけすぎていないか確認する” など、保護者が適宜確認・管理をするようにしましょう。
“パソコンを連続して使って良いのは1時間だけ” など、”パソコン使用のルール” を設けたり、”ブルーライトをカットする子ども用メガネ” を着けたりといった、視力悪化防止対策をするのがおすすめです。
デメリット2. 依存症になる可能性がある
子どもにパソコンを与えるデメリットの2つ目は、”依存症になるリスクがある” という点です。
子どもが “調べものだけ” でパソコンを活用しているなら、とくに心配する必要はないのですが、パソコンで “ゲーム” をしていたり、”友達とのメール・チャットのやりとり” に夢中になったりすると、パソコン依存症になる可能性があります。
また、延々とYouTubeなどの動画配信サイトで動画を見続けていたりすると、“生活リズム崩れてしまうリスク” もあるので注意が必要です。
睡眠時間が大幅に減ったり、他の勉強がおろそかになったりしないためにも、子どもにパソコンを与えるときは、保護者がしっかりと管理し、パソコンの使用時間に関するルールを事前に決めておくようにしましょう。
デメリット3. 個人情報の漏洩
子どもにパソコンを与えるデメリットとして、”個人情報の漏洩リスクがある” という点は、要注意のポイントです。
インターネットを利用すると、不適切なサイトへのアクセスや、個人情報の投稿・アップロードが原因で、”個人情報の漏洩問題” が発生するリスクがあります。
顔を知らない “ネット友達” とコミュニケーションをしたことが原因で、ネット上でのイジメやトラブルに巻き込まれることも少なくありません。
大人でも個人情報漏洩やプライバシー侵害、悪質ないじめなどのトラブルに発展するリスクがある中、予備知識が少ない子どもがインターネットを使うとなると、よりトラブルに巻き込まれる危険性が増します。
子どもにパソコン、とくに、インターネットを使わせるときは、保護者として、子どもにネットリテラシーを教え、不正アクセスが出来ないようパソコンの設定を見直しておくことが必要です。
このように、子どもにパソコンを与えることは、たくさんのメリットがある一方で、Web上のトラブルに巻き込まれる、インターネット依存が強まるなどのデメリットもあります。
子どもにパソコンを与えるときは、メリットだけでなく、デメリットを理解した上で、”親子でパソコン使用のルールを決める” など、しっかり対策をしてから与えるようにしましょう。
子どもにパソコンを与えるのは何年生から?

子どもにパソコンを与えるのは、読み書きを覚えてきた “小学校2年生〜3年生” がベストだと言われています。
小学校3年生になると、学校の授業でパソコンを使う機会が増えるケースが多く、パソコンの授業が始まったときに、理解できず苦手意識が生まれないよう、小学校2年生頃から触れさせておく保護者も少なくありません。
子どもにパソコンを与える時期に明確な決まりはないものの、読み書きができてきた段階で、少しずつパソコンの使い方を覚える機会を作って見るのが良いでしょう。
ただ、先述の通り、子どもにパソコンを与えるメリットがある一方で、”視力低下のリスク” などのデメリットもある点には配慮が必要です。
子どもにパソコンを与え始める頃は、”1日の使用時間を30分まで” という約束を決め、子どもがパソコンの使用に慣れてきたら、徐々に使用時間を伸ばしていくなど、保護者がしっかりと管理できる体制を作ってみてください。
メリット・デメリットを理解して、子どもにパソコンを与えよう!

このように、インターネットの普及が進む現代において、子どもに早いうちからパソコンと触れ合う機会を作ることは、子どもの将来にさまざまな好影響を与える可能性があります。
できれば、小学校2年生・3年生など、読み書きができるようになってきた段階で、パソコンを使う機会を少しずつ増やしていくと良いでしょう。
ただ、”パソコン使用のルール” を決めないと、長時間パソコンを利用するようになり、”インターネット依存症” や “視力低下” など、子どもの成長に悪影響を及ぼす危険性もあります。
また、知らないうちに子どもが家の写真や、家族の名前、住所などをWeb上にアップロードしてしまい、個人情報が漏洩するなど、トラブルに巻き込まれるリスクもゼロではありません。
子どもにパソコンを与えるときは、”保護者の目の届く範囲で利用する” などのルールを定め、放置するのではなく、保護者がしっかりと管理するようにしましょう。




